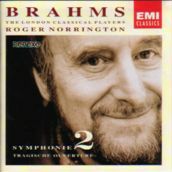ブラームス演奏ノート
交響曲2番と悲劇的序曲のライナーノートから
私たちはここに、演奏の歴史をたどってきた長い道のりのほぼ終点近くに立っています。30年の間、私たちはゆっくりと、しかし確実に中世とルネッサンスから、初期と後期のバロックを経由し、古典派と初期ロマン派へと進んできました。今こうしてブラームスまで到達し、私たちは我々の祖父の時代にあたる作曲家の作品を検証し、新しい光を当てようとしているのです。これは価値のある試みでしょうか? その当時、物事はそれほど違っていたのでしょうか? 楽器や演奏スタイル、技術、音楽的なアプローチ、こういったものは、全て注目し研究するに値するほど変化しているのでしょうか?
そう、まず最初に、私たちは125年前のことを話しています。それを考えてみると:1870年の125年前とは、バッハやヘンデルがまだ生きている時代でした。1876年−ブラームスの交響曲第1番の初演の年−からは長い年月が流れており、その間に、帝国主義、ファシズム、共産主義の解体だけではなく、多くの政治的、文化的な大変動がありました。
第2に、想像するよりはるかに多くのことが音楽的に変化しました。楽器、オーケストラの規模、シーティング(配置)、技術、スタイル、これら全てのことが、少なくともブラームスの死後50年のうちに重大な変更を受けているのです。最初のレコード録音は、これらの変化の何年も後に生まれました。歴史的な視点を求めるに当たって、そこからはごく限られたことしか期待できません。
第3に、ブラームスは彼が偉大な古典派の作曲家たちの最後の位置を占めるという理由から、真剣な再評価の対象となります。その流れは明らかに、ハイドンとベートーベンから、シューベルト、メンデルスゾーン、シューマンを経てブラームスに至っています。もちろん、彼はワーグナーの時代に生きており、新しい楽派に伴う音楽のスタイルの大きな変化から彼の音楽の演奏も影響を受けなかったわけではありません。しかし、それは歴史の偶然です。ブラームスは一時、リストやワーグナーの「未来の音楽」に強く反発しました。恐らく、これだけ時代が経ってから見れば、非常に異なるワーグナーの伝統から彼の音楽を切り離し、彼固有の「古典的ロマン主義」を際だたせることは、相対的に易しいことでしょう。
歴史的な適切さを真剣に考えるLCPと私は、これらのプロセスに特別な共鳴を感じます。なぜなら、ブラームスは音楽学に深くかかわった最初の作曲家だからです。彼自身の関心は、シューマン、シューベルト、ベートーベン、ハイドンといった作曲家から、遥か古くにさかのぼります。彼はバッハ、ヘンデル、クープラン、シュッツ、さらにはパレストリーナまで演奏したり校訂したりしました。彼は、私たちと同じように、これらの音楽が自分の時代にどのように適合するのかということを考えました。興味深いことに、こうした音楽を聴いたり演奏したりすることに、彼やその同時代の人々より私たちの方がはるかに親しんでいます。しかし、これと呼応するように、私たちは彼自身の音楽の内部にもそれらの残響を感じ、彼と過去とのつながりを味わい楽しむことができるのです。
この録音に収めた2つの作品はブラームスが最も自信を持っていたものです。これらはいずれも1870年代後半に作曲されました。そのころレクイエムと交響曲第1番の成功によって、彼は室内楽作曲家として限定していたレパートリーから自らを解き放ち、オーケストラというメディアの扱いをマスターしたのです。
『悲劇的序曲』は極めて劇的で激しい作品で、交響的作品の第1楽章の形態(ドナルド・トヴェイの意見では彼の作品中最高のできばえ)を持っています。第2交響曲はよりリラックスして叙情的ですが、優しさと力強さの素晴らしい複合体です。
私は第1交響曲は「クララ・シューマン」交響曲であると主張しました(第1交響曲のライナーノート)。第2はその後すぐに作曲され、「クララの」ホルンの呼び声が冒頭に現れることから、この音楽の暖かさと喜ばしさもまたブラームスの希望の星への霊感に負うところが大きいと考えられるでしょう。第1楽章44小節目の喜びの表現を見てみましょうか? とろけるような主題、それは最初耳にするとこの楽章の主旋律であるようにも響きますが、消えてしまった後は展開部でも再現部でも再び聞こえることはありません。このような非対称性は、ブラームスの「古典」形式の豊かな独自性を示す一例であり、実際、彼の劇的な感性を示すものです。
このような素晴らしい音楽を、1870年代の楽器を用い、適切なスタイルを探りながら演奏することは、まさに挑戦です。これはLCPと私が数年かけて行ってきたベートーベン、シューベルト、メンデルスゾーン、シューマンの詳細な研究なしには実現できないものでした。私たちが実践したいくつかのツールと演奏の狙いをここで見てみることにしましょう。
オーケストラ
1870年の弦楽器は構造の点では現代のものと違いはありませんでした。それらは全て19世紀の仕様に基づいて作られていたか、(もし古いものであったら)同世紀の初期のうちに改造されていました。しかし、弦はガットのものが用いられ、調律は現在よりも一般的に低く、A=435程度でした。同様に、木管楽器は古典派の時代より著しく「改善」されていましたが、現代のものほど複雑でもなく強化されてもいませんでした。ティンパニは、言うまでもなく、プラスティックではなく革張りであり、トロンボーンは近代のような大きな口径を持ってはいませんでした。
ブラームスのホルンとトランペットに対する姿勢は興味深いものです。彼は新しいバルブ・ホルンより手を使う古いホルンの方を好むと公言していましたし、半音階を吹ける楽器は過去40年にさかのぼって存在しなかったかのように、限定された「古典的」トランペットのパートを書きました。けれども、ブラームスが聴いたり指揮したりしたオーケストラはどれもバルブ・ホルンを使用していたので、私たちはここでもそれを採用することにしました。初期のバルブ・ホルンは、一体型でむしろ軽量の楽器で、その音は現代の重い、部品化された(compartmentalised)ものとは随分異なっています。
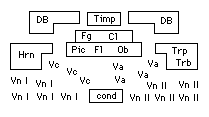 オーケストラの配置は、1750年から1950年までの期間を通して、第1バイオリンと第2バイオリンが舞台の反対側に座ったもので、さらに私たちの場合はホルンとトランペットも同様に並んでいます。ダブルベースは、ヘンシェルがブラームスと議論しつつ初期のボストン交響楽団で試みた形態、木管の後ろの両サイドに分割して配置しています。
オーケストラの配置は、1750年から1950年までの期間を通して、第1バイオリンと第2バイオリンが舞台の反対側に座ったもので、さらに私たちの場合はホルンとトランペットも同様に並んでいます。ダブルベースは、ヘンシェルがブラームスと議論しつつ初期のボストン交響楽団で試みた形態、木管の後ろの両サイドに分割して配置しています。
私たちが一番驚いたのはオーケストラの規模でした。1870年代のドイツのオーケストラは、、一般に依然としてメンデルスゾーンがゲバントハウスを指揮していた1830年代と同じ人数で構成されていました。8〜10人の第1バイオリンが伝統であり、もちろん、そうした(近代と比べて)小さい編成は、弦楽器と木管、金管との自然なバランスに深い影響を与えています。そう、ハイドンやベートーベンの時代の慈善演奏会の場合と同じように、祝祭のための大規模なオーケストラもあったことは事実です。けれども、こうした機会にはそれに合わせて木管は倍管にするのが普通でした。ウィーン・フィルは特別に大きな弦パート(と高いピッチ)を持っていたので、常にそうしていました。しかし、他のオーケストラの場合、平均的な構成は、36の弦(平均して各声部に9ずつ)、9の木管と9の金管と考えることができます。
ブラームスのスコアの書法からは弦、木管、金管の3つの対等な声部がはっきりと読みとれます。私はこれを見て、彼がかつてウィーンで学び、指揮したガブリエリやシュッツの3声のモテトを思い浮かべます。近代の「壁から壁まで」並んだ70人もの弦楽奏者が彼の音楽を表現するのに絶対必要であるとは、どうしても考えられません。この録音において、私たちは皆さんに、ブラームスとその周辺にとっては明らかに標準的だったバランスを体験していただく機会を提供します。
演奏技法
私たちの歴史的検証のあらゆる段階で、非常にたくさんの同時代の証拠を見いだしたのは素敵な驚きでした。必然的に、弦楽器の演奏がその時代のオーケストラのスタイルを決定づけることになります。そしてちょうどクァンツがヘンデルとバッハについて、レオポルド・モーツアルトがハイドンとウォルフガングについて、シュポアがベートーベンについて、そしてバイヨーがベルリオーズについて教えてくれたように、大ヨアヒムが、ブラームスの時代の演奏について直接の証拠を与えてくれます。ブラームスのごく親しい友人であったヨアヒムは、ブラームスと同様に、シューマンの庇護を受けた、極めて古典志向の演奏家でした。もちろん、彼の証言(1904年のモーザーとの共著『バイオリン教本』)はそれぞれの音符をどのように弾くべきか「正確に」は教えてくれません。しかし、わずかに残されたヨアヒム自身の録音とあわせて考えるとき、それは少なくとも失われた伝統に対する多くの洞察を与えてくれるのです。
この伝統が、近代になって失われるまで、どれほど長い間大切に守られてきたかという点には驚きを禁じ得ません。なぜならヨアヒムはビオッティにまでさかのぼるバイオリン教師の流れをすっかり受け継いでおり、彼のスタイルはモーツアルトの時代とほとんど違わないのです。そう、運弓法はバラエティに富むようになり、シュポアやバイヨーの頃よりもスピッカート奏法が広まっていたことは事実でしょう。しかしヨアヒムは、「パガニーニ様式」の左手と右手の体操は「真の古典派様式」をねじ曲げるものであり、「楽器の本性を否定するもの」であり、大き過ぎるあるいは使いすぎるビブラートや誤ったポルタメントの使用は「内面的な感情が欠落したときの自然な表現の代用品」に過ぎない、こういった議論に全面的に同意していたのです。
ヨアヒムは、ポルタメントとビブラートをいつ、どのように、どれくらい使うべきかをはっきりと説明しています。彼は、弦に弓をのせたままでのスタカートを、弾ませる奏法と同じく重視していました。彼は滑らかなポルタートが依然健在であること、バッハの時代と同じように、対になった、あるいはグループになった音符は異なった重みを持つべきだということを示しています。彼は統一された弓使いは一般的には良いことだが、ゆっくりした表情豊かな音楽の長いフレーズを弾くには誤りという場合もあると述べています。何よりも彼は、フレージングは「話すように」しなければならないこと、弦楽の伝統の原点はイタリアのベルカントの「高貴な朗詠(cantilena)」であること、「古典的な運弓の技術」は歌うように自由であり、楽器の音は「客観的に美しく」、荒々しかったり「不自然な強弱のばらつき」があってはならない、こういうことを要求しているのです。
オーケストラにおいては、ポルタメントやビブラートは独奏者の場合より一層控えめであったでしょうが、私たちは彼が示唆するところではどちらも用いています。同様に、木管と金管のアーティキュレーション、弦楽器のボウイングのあらゆる面において、私たちは自分の技術が、当時一般に期待されていたこと、なかんずく演奏している音楽が求めることを実現するものであるように、努力を払っているのです。
演奏スタイル
ブラームスのもう一人の親友であり、ボストン響とロンドン響の創設者であるジョージ・ヘンシェルは、若い頃、各地を演奏して回る大指揮者の時代になる前には、いわゆる「解釈」というものはなかったと語っています。人々は音楽を最善を尽くして演奏するだけで、他と比較するための経験というものはほとんどありませんでした。今日、演奏スタイルについて語るとき、私たちは必然的に極めて主観的な意見の世界に入り込むことになります。実際、演奏は非常に個人的なものでなければ優れたものとはみなされません。げれども、私たちの考えでは、そうした創造性さえあれば、ある時代、作曲家、作品にとって適切な音楽表現であると演奏者が考えることを自らの個人的感覚にぶつけてみなくても良いということにはならないはずです。この試みで私たちが見つけようとしたのは、大きく言えばスピード、フレージング、性格といったことでした。
ブラームスは彼の作品にほとんどメトロノーム指示を残していません。このことから彼は自分の作品がいつも同じ速さで演奏されることを欲しなかったと考えることもできるでしょう。しかし伝統全体が失われてしまうと、Adagio non troppoというような単純な言葉は曖昧で歯がゆいものとなります。ブラームスが適切だと考えたであろうスピードの範囲を探るにあたって、わたしたちはわずかに残されたメトロノーム指示(『悲劇的序曲』と第2交響曲にはひとつもありませんが)を調べ、同時代の記述に目を通すことができます。フリッツ・シュタインバッハの詳細なスコアへの書き込みとマイニンゲン交響楽団のためのコメントは大変多くのことを明らかにしてくれます。また1877年のリヒターの演奏時間(最初の繰り返しを含めて43分)とビューローの時間(繰り返しなしで38分)からは、活発なアレグロというだけではなく、明らかに「古典的」緩徐楽章もぐずぐずしたものではなかったことが分かります。
楽章中でのテンポの変動は自然な、また記録もよく残された19世紀の演奏スタイルの特徴です。この習慣を作り上げたのはワーグナーによるところが大とされていますが、ブラームスの歯切れの良い反論によれば:「テンポの変動というのは別に新しいことではありませし、それは分別を持って(con discrezione)行われなければなりません。」ブラームスの音楽は、彼の生前、ニキシュのような極端な変更を行う指揮者によっても、ワインガルトナーのようなより古典的な演奏家によっても、等しく演奏されました。彼はどちらにも満足していたことでしょう。最終的には、もちろん、それは個人的な好みと直観の問題です。しかし、ブラームスの「分別を持って」という言葉は強調しておく価値があります。それはヨアヒムの「バイオリン教本」の明快な格言とつながりがあります:音楽は「生き生きとした精神」でなければならないが、テンポの変動は「メトロノームによってはじめてその変化が分かる」程度のわずかなものにとどめるべきである。スピードの変動は、公開の、オーケストラ音楽においては、明らかに激しいものではなく微妙なものだったはずです。
私たちのブラームスへのアプローチの狙いは次のように要約することができるでしょう:
テンポ:雄大しかし率直、テンポの変化:繊細しかし単純、テクスチュア:ポリフォニー音楽の書法のように明快、バランス:木管のバランスを回復、動作:「音」と同じくらい重要。十分「歌い込んだ」フレージング、暖かみ、情熱そして溌剌。
ブラームスの音楽は色々な方法で演奏できます。彼は、18世紀の音楽家のように特定の場所や機会のために作曲したのではなく、少なくとも大ドイツ全体のために書きました。ただひとつの「正当な」演奏は言わずもがな、彼の音楽を演奏する唯一の方法などありません。詳細な歴史的視点を取るということの面白さは「指示に従う」ということではなく、十分信頼するに足る情報を、自分自身の現在の音楽性とイマジネーションにマッチさせることなのです。オリジナル楽器を用い当時のスタイルを採用しても、私たちが古めかしくなければならないということはありません。反対に、その結果音楽が全く新しく響くことすらあります。私たちは偉大な作品をもう一度考え直し、新しく蘇らせることができるのです。
このブラームス・プロジェクトへの協力と助言に対して次の方々にお礼を申し上げます:カール=ギュンター・アーレン博士、クリーブ・ブラウン博士、ウィル・クラッチフィールド、クリストファー・ダイメント、ウィリアム・マーロッホ、ロバート・パスカル教授。
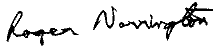 ロジャー・ノリントン
ロジャー・ノリントン
(*第1交響曲のライナーノートも基本的に同じ文章ですが、1番の演奏についてもう少し詳しい記述があります。当然のことながら、そのかわり第2交響曲に関する記述はありません)